
こんにちは、いとう(@batatlife)です。
今回は、村山昇さんの『働き方の哲学』について、解説していきたいと思います。
あなたは「仕事」って言葉を聞いて、どんな気持ちになりますか?
ワクワク?それともため息?
実は、その反応こそが、あなたの「仕事観」を表しているんです。
そんな仕事に対する個人の考え方や価値観について、考えてみましょう。
仕事の悩み、どこから来るの?
「月曜日が憂鬱…」「この仕事、もう限界かも…」なんて思ったことありませんか?
でも、ちょっと待って。
同じ仕事をしているのに、ある人は楽しそうにやっているし、ある人は苦しそう。
これって、なんでだと思います?
答えは意外と単純。
それは「仕事観」の違いなんです。
つまり、仕事をどう見るか、どう捉えるかによって、同じ仕事でも全然違って見えるんです。
例えば、こんな感じ↓
- Aさん:「仕事は生活のため。お金を稼ぐ手段でしかない」
- Bさん:「仕事は自己実現の場。自分の能力を発揮する機会」
同じ仕事をしていても、Aさんは毎日憂鬱かもしれません。
でも、Bさんは充実感を感じながら働けるかもしれません。
この違い、すごくないですか?
「健やかな仕事観」って何?
じゃあ、どんな仕事観を持てばいいの?って思いますよね。
村山さんは「健やかな仕事観」を持つことが大切だと言っています。
「健やかな仕事観」って何?簡単に言うと↓
- 自分の価値観と合っている
- 社会のためになる
- 成長できる
この3つがバランスよく含まれている見方のことです。
例えば、「この仕事は、自分の得意なことを活かせるし(自分の価値観)、お客さんに喜んでもらえるし(社会のため)、新しいスキルも身につく(成長)」なんて考えられたら最高ですよね。
先人の知恵を借りよう
さて、ここからが本題。
「健やかな仕事観」を作るのに、先人たちの知恵を借りてみましょう。
村山さんの本には、古今東西の偉人たちの考えがぎゅっと詰まっているんです。
アダム・スミスの「見えざる手」
経済学の父と呼ばれるアダム・スミス。
彼は「見えざる手」という概念を提唱しました。
簡単に言うと、「自分の利益を追求することが、結果的に社会全体の利益につながる」というもの。
でも、「自分の利益だけ考えりゃいいの?」って思いますよね。
スミスが言いたかったのは、「自分の仕事が社会にどう貢献しているか」を意識することの大切さなんです。
例えば↓
- パン屋さん:「おいしいパンを作って売ることで、お客さんを幸せにできる」
- プログラマー:「使いやすいアプリを作ることで、人々の生活を便利にできる」
こんな風に、自分の仕事の社会的意義を見出せると、やりがいが全然違ってきますよね。
マックス・ウェーバーの「天職観」
次は、社会学者のマックス・ウェーバー。
彼は「天職観」という考え方を示しました。
簡単に言うと、「仕事は神から与えられた使命」という考え方です。
「えっ、宗教的な話?」って思うかもしれません。
でも、現代風に解釈すると、「自分の仕事に使命感を持つ」ということ。
つまり、「この仕事は自分にしかできない」「社会のためにこの仕事をする」という意識を持つことなんです。
例えば↓
- 教師:「子どもたちの可能性を引き出すのは、私の使命だ」
- 医者:「患者さんの健康を守るのは、私にしかできない仕事だ」
こんな風に考えると、普段の仕事も特別な意味を持ってきませんか?
ピーター・ドラッカーの「自己実現」
経営学の巨人、ピーター・ドラッカー。
彼は「知識労働者」という言葉を生み出した人です。
ドラッカーは、仕事を通じて「自己実現」することの重要性を説きました。
「自己実現」って聞くと難しそうですが、要は「自分の可能性を最大限に発揮すること」。
つまり、仕事を通じて自分を成長させ、能力を発揮することなんです。
例えば↓
- デザイナー:「新しいデザインに挑戦することで、自分の創造性を高められる」
- 営業マン:「お客様のニーズを理解し、最適な提案をすることで、コミュニケーション能力が磨かれる」
こんな風に、仕事を自分の成長の機会と捉えられると、毎日が楽しくなりそうじゃないですか?
仕事観を変える、3つのヒント
さて、ここまで偉人たちの考えを見てきました。
でも、「そんな偉い人の考えを、どうやって自分の仕事に活かせばいいの?」って思いますよね。
そこで、具体的なヒントを3つ紹介します。
「3人のレンガ積み」の話
昔々、3人のレンガ積み職人がいました。
彼らに「何をしているの?」と尋ねると、こんな答えが返ってきました。
- 1人目:「レンガを積んでいる」
- 2人目:「壁を作っている」
- 3人目:「大聖堂を建てている」
同じ仕事をしていても、捉え方が全然違いますよね。
1人目は目の前の作業だけ、2人目は少し広い視野、3人目は大きな目的を見ています。
あなたの仕事は、どんな「大聖堂」を建てているんでしょうか?
例えば↓
- コンビニ店員:「地域の人々の生活を支える拠点を作っている」
- 経理担当:「会社の健全な運営を支え、従業員の生活を守っている」
こんな風に、自分の仕事の大きな意義を考えてみると、毎日の仕事も違って見えてきませんか?
「価値創造回路」を意識する
「価値創造回路」って聞いたことありますか?
簡単に言うと、「自分→会社→顧客→社会」という流れのこと。
つまり、自分の仕事が最終的に社会にどんな価値を生み出しているかを考えるんです。
例えば、ソフトウェア開発者の場合↓
- 自分:プログラミングスキルを活かす
- 会社:新しいアプリを開発
- 顧客:便利なアプリを使える
- 社会:生活の質が向上する
こんな風に、自分の仕事が社会にどんな影響を与えているか考えてみると、「ああ、自分の仕事って意味があるんだ」って実感できますよね。
「内的キャリア」を大切にする
内的キャリアとは「自分の内面的な成長や満足感」のこと。
対義語は「外的キャリア」で、これは肩書きやお給料など、外から見える部分です。
どっちも大切ですが、長い目で見ると「内的キャリア」の方が重要だと言われています。
なぜなら、それが本当の意味での「やりがい」や「生きがい」につながるからです。
例えば↓
- 新人時代:「基本的なスキルが身についた!」
- 中堅時代:「後輩の成長を手伝えるようになった!」
- ベテラン時代:「自分の経験を活かして、会社の問題を解決できた!」
こんな風に、自分の内面的な成長を意識することで、日々の仕事にも新しい意味が見出せるんです。
仕事観を変えると、何が変わる?
ここまで、仕事観を変えるヒントをいくつか紹介してきました。
でも、「そんなの簡単じゃないよ」って思う人もいるかもしれません。
確かに、急に考え方を変えるのは難しいかもしれません。
でも、少しずつでも仕事観を変えていくと、こんな変化が期待できるんです:
- モチベーションが上がる
同じ仕事でも、その意義や価値を見出せると、やる気が湧いてきます。
「なんでこんな仕事してるんだろう…」から「よし、がんばろう!」に変わるかも。 - ストレスが減る
仕事の意味を理解できると、多少の困難も「成長のチャンス」と捉えられるようになります。 - 創造性が高まる
「言われたことをこなす」だけでなく、「もっと良い方法はないか」と考えるようになります。 - 人間関係が良くなる
自分の仕事の価値を理解すると、周りの人の仕事の価値も理解できるようになります。
結果、協力的な関係が築けるように。 - キャリアの方向性が見えてくる
「自分は何がしたいのか」「どんな価値を生み出したいのか」が明確になると、将来のキャリアプランも立てやすくなります。
あなたの「仕事観」は?
さて、長々と書いてきましたが、いかがでしたか?
「仕事観」って、案外奥が深いですよね。
ここで、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。
- あなたは今、どんな「仕事観」を持っていますか?
- その「仕事観」は、あなたを幸せにしていますか?
- もし変えるとしたら、どんな「仕事観」を持ちたいですか?
正解はありません。
でも、考えることに意味があるんです。
なぜなら、それがあなたの「より良い仕事人生」への第一歩になるかもしれないから。
村山さんの本には、もっともっと深い洞察がたくさん詰まっています。
「πの字思考プロセス」「七放五落十二達の法則」など、面白い概念がいっぱい。
興味が湧いた人は、ぜひ読んでみてくださいね。
最後に、こんな言葉で締めくくりたいと思います。
「仕事は生きること。生きることは、自分を表現すること」
あなたの仕事が、あなたらしさを輝かせる舞台になりますように。
そして、それが社会に素敵な価値を生み出しますように。
では、また次回。
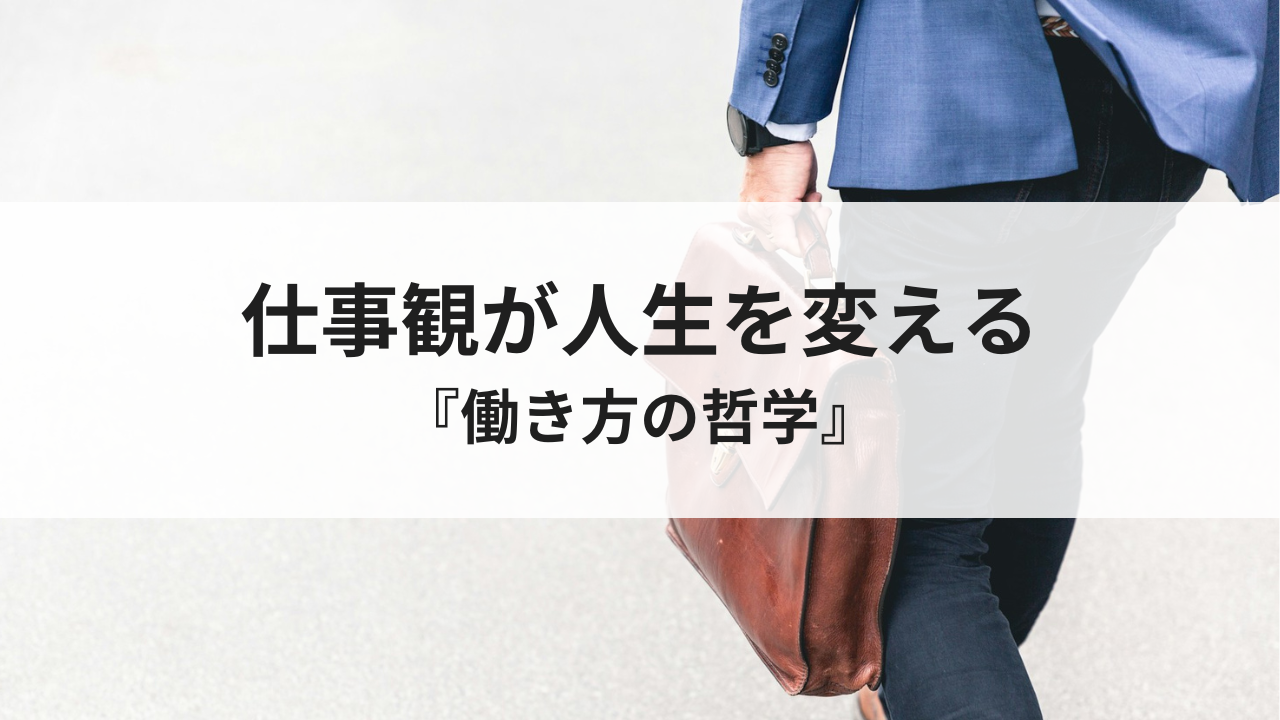
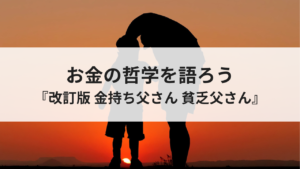
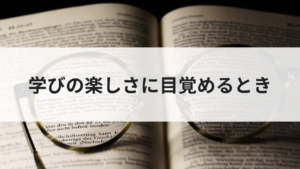
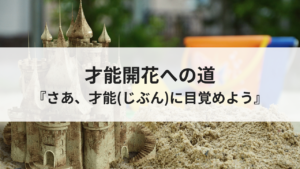
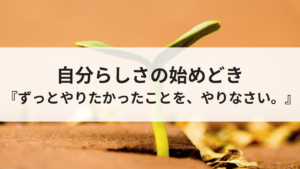

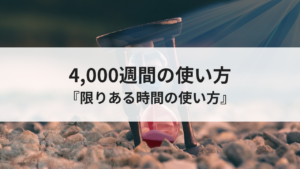
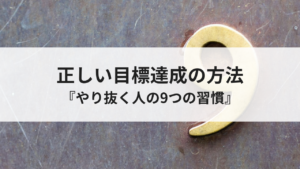
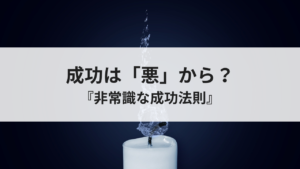
コメント